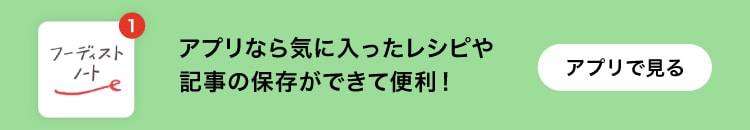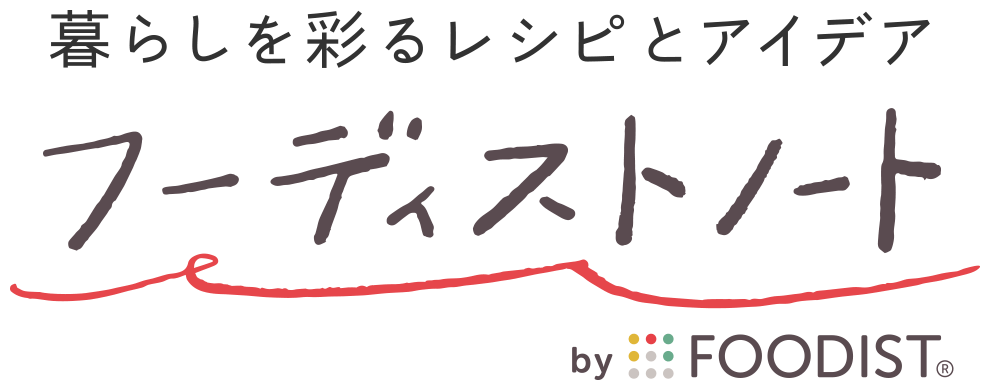臭みをとっておいしく食べるには?下ごしらえや保存方法は?「ぶり」の基本のき

覚えておこう!「ぶり」の上手な選び方

店頭で並ぶぶりは、一尾よりも切り身が多いですよね。切り身には背身と腹身があり、背身は上の写真のように皮の色が濃く、さっぱりした味わい。これに対し、腹身は皮の色が白っぽく薄めで脂がのってこってりしています。
背身と腹身のどちらにするかは、さっぱりめがいいか、こってりめがいいかお好み次第。部位を決めたら、次にチェックしたいのは鮮度です。血合いの色が褐色よりも、鮮やかな赤色をしているものを選びましょう。身にハリやツヤのあるものが新鮮ですよ。
もし一尾を選ぶなら、尻尾がピンと張り、黄色の縞模様が鮮やかではっきりしているものがおすすめです。
下ごしらえの霜降りで「ぶり」をもっとおいしく♪
霜降りの仕方
ぶりをはじめ、魚には独特の臭みがあります。煮付けるときは、煮汁に臭みが移ることがあるため、霜降りをしましょう。熱湯を回しかけるか、熱湯にサッとくぐらせてから冷水に取ります。表面を洗い、水気をしっかり拭けばOKです。
また、ぶりは脂が多いため、脂がじゃましてたれや塩のしみ込むスピードがゆっくりになりがち。煮付けや塩焼きにするときは、他の魚よりも長めに漬けたり、早めに塩を振ったりすることを心がけてくださいね。
下ごしらえで手に付いた魚の臭いを消す方法
下ごしらえの際、魚独特の「生臭さ」が手に付いてなかなか取れないこと、よくありますよね。そのことが理由で魚料理を避けてしまうことも少なくありません。
独特の生臭さを発する正体は「トリメチルアミン」と呼ばれる物質です。元々魚が持っている「トリメチルアミンオキシド」という物質が時間とともに分解され、トリメチルアミンに変化することで発生します。そのため、魚自体の生臭さを最小限にするためには、なるべく新鮮な状態で調理するのがポイント。
手に付いた臭いを消すには、
・手のひらに塩をまぶしてもみ洗いする
・柑橘類の皮をつぶし、その汁でこすり洗いする
・酢水に手を入れ、こすり洗いする
・ステンレスに触れる
といった様々な方法があります。最後のステンレスに触れる方法は、専用のアイテムも発売されているので魚料理をよくする方は購入するのもおすすめです。ボールやシンクに触れてから手を洗うという方法もありますよ。
ぶりの保存方法
スーパーでおいしそうな「ぶり」を買っても、そのまま冷蔵庫に入れておくだけだとすぐに傷んでしまいます。買ってきたらすぐにひと手間かけて、鮮度をキープしてくださいね。
冷蔵保存
ぶりを冷蔵保存する手順は以下の通りです。
1. 表面についた水分をキッチンペーパーで拭きとる
2. 1切れずつラップで包む
3. 密閉できる保存袋に入れる
そのまま保存すると表面が空気に触れて酸化するだけでなく、ドリップに雑菌が繁殖して、臭みの原因になります。手間ではありますが、水分を拭き取り空気に触れないようにしましょう。
冷凍保存
ぶりを冷凍保存するときも、基本的には冷蔵保存の1~3の手順と同じですが、1の手順の前に両面にまんべんなく塩をふりかけて冷蔵庫で10~15分ほど寝かせ、水分を出してから拭き取るのと臭い対策や鮮度キープにつながりますよ。また、保存をするときには、アルミトレーにのせるようにすると冷凍速度を早めることができておすすめです。ゆっくり凍らせてしまうと鮮度の低下や臭みの原因になるため、ひと工夫して冷凍速度を早めることが重要です。
解凍する際は、冷蔵庫で自然解凍しましょう。なお、一度解凍されたぶりの再冷凍は雑菌が繁殖する可能性があるため控えましょう。
ぶりを冷凍するときは下味を付けて冷凍する「下味冷凍」もおすすめです。調味料がぶりに付くことで乾燥を防ぎ、食感や色を悪くする「冷凍焼け」を予防します。また、冷凍することで味がしみ込み調理時間の短縮に。忙しい夕食作りにおすすめの冷凍方法です。
「ぶり」の王道レシピ
ぶりの選び方や下ごしらえ、保存方法などのポイントを押さえたら、ぶりを使った料理を作ってみましょう。まずはぶり大根や照り焼きといった王道メニューをご紹介します。
こってり仕上げる「ぶり大根」
黄金比で簡単!ぶりの照り焼き
シンプルがおいしい!ぶりの塩焼き
食べ方いろいろ♪「ぶり」のアレンジレシピ
定番の食べ方もおいしいですが、ぶりは意外にもアレンジ自在なんです。ぶり料理のレパートリーをもっと増やしましょう♪
ご飯がすすむ!ぶりのソースカツ風
寒い日にオススメ!ぶり大根のクリーム煮
ワインのおつまみに!ぶりのアヒージョ
ほぐしておいしい!ぶりのはんぺんサンド
「いなだ」も「はまち」も「ぶり」になる?
ぶりのおいしい食べ方をご紹介したところで、ぶりに関するちょっとした豆知識もご紹介します。

魚には「出世魚」と呼ばれるものがありますが、成長に応じて呼び名が変わる魚に対して使われる言葉で、「すずき」や「ぼら」、そしてぶりも同じく出世魚。
呼び名は地域によってさまざまですが、おおむね関東では「わかし→いなだ→わらさ→ぶり」、関西では「つばす→はまち→めじろ→ぶり」。
80cmほどになった成魚を「ぶり」と呼ぶのは全国共通です。「はまち」は、ぶりの若いころの呼び名なんですね。ぶりは養殖もさかんで、中型サイズで出荷されることが多いため、養殖のぶり全体を「はまち」と呼んで区別しているそうです。
ちなみに、どうして呼び名が変わるの?
「出世魚」という呼び方の由来ですが、江戸時代までの日本では、武士や学者が元服や出世したときに名前を変えていました。それにちなんで、成長過程で呼び名が変わる魚を「出世魚」と呼ぶんだそうですよ。
魚は大きさによって、味や調理の方法などが変わり、価値や値段も違ってきます。それらを漁師さんや流通の場で区別するために、成長の過程で呼び名を変えることは流通面でもメリットがあるという訳です。ぶりをおいしくいただいて、その出世パワーにあやかりたいですね。
「寒ぶり」と「ぶり」の違いって?
「寒ぶり」とは、11月~2月ころの真冬に獲れるものをさします。真冬以外の時期に水揚げされたり、養殖されたりしたものはシンプルに「ぶり」と呼ばれています。寒ぶりは、身が締まり脂がのって旨みが増しておいしいですよね。
富山県の「ひみ寒ぶり」や新潟県の「佐渡一番寒ぶり」は有名で、高級ブランドとして人気があります。味もさることながら、お値段も最高級!
ところで、ぶりは漢字で「鰤」と書きますよね。12月(師走)に最もおいしくなる魚のため、魚へんに「師」というわけなんです。
臭みを取ってワンランク上のぶり料理を
出世魚の代表ともいえるぶりは、縁起がよくおせち料理にも使われ、贈答用にも喜ばれますよね。フレッシュなぶりを選び、上手に下ごしらえして、旬のおいしさをめいっぱい楽しみましょう。
※参考ホームページ
BEST TIMES「魚のプロが教えるおいしい切身魚の選び方」
三重県「おさかな図鑑/ブリ」
ダイエー「ぶりの下ごしらえ(煮物の場合)」
Z-SQUARE「魚の生臭さを抑えるコツ」