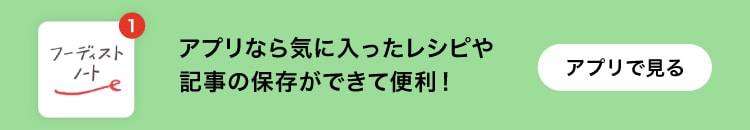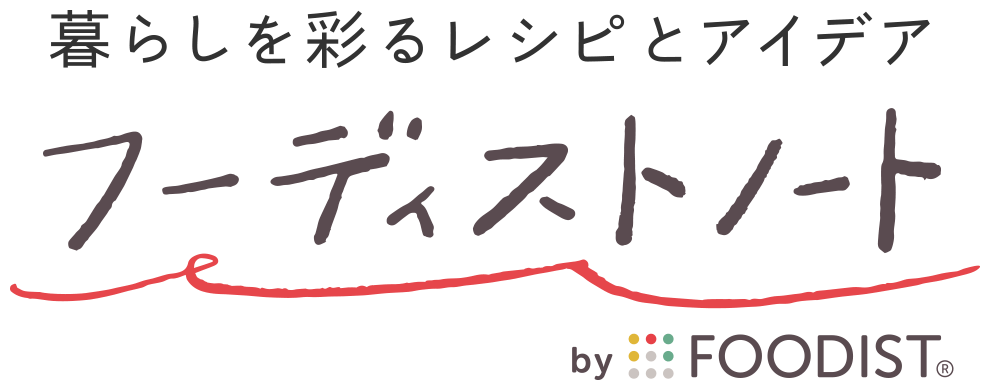「片栗粉の適量」って?少なくてとろみがつかない、多すぎてどろどろになる問題を解消!
目次
こんにちは!かな姐です。
寒くなってくるとあたたかい汁物や鍋料理、麺類が恋しくなりますよね。
一人暮らし中の長女が先日、仕事帰りに「晩ごはん何作ろうかなー」とわたしに相談のLINEをしてきていたのですが、あーだこーだとアドバイスしているうちに結局その日はキムチ鍋にしたようで、
「一人暮らしを始めてから、冬になると毎日鍋してるって言ってた兄さんの気持ちが今になってよくわかるようになった」
と言っていました(笑)
明かりのついていない寒い部屋に帰ったときに食べたいものは鍋しか思いつかないそうです。なるほどなーー!
さて、そんな寒さ厳しい今日この頃ですが、今回のお悩みはこちらを取り上げてみました。
今回のお悩み相談:「片栗粉の適量」がどのくらいの量なのかわかりません
・「片栗粉…適量」とレシピによく書いてありますが、どのくらいの量なのかいまいちわかりません。
・私は粉との付き合い方がよくわかりません。
片栗粉の量について!
レシピの分量でよく見かける「適量」という言葉ですが、きちんとした正解の量ってあるのでしょうか?
片栗粉が出てくるレシピといえば、
・から揚げなどの衣に使う
・ひき肉などの生地のつなぎとして使う
・水分の多い料理の仕上げに加えてとろみ付けに使う
主にこの3つの調理のときですが、なぜ適量と書かれているかというと、食材の持っている水分量や、加熱時にどれほど水分が蒸発してしまったか、水切りがどれほどできたかなど、そのときの調理の状態や食材の状態によって微妙に差が出てくるからなのです。
から揚げの衣については別の記事でお答えしたので、
から揚げは薄力粉で作る?それとも片栗粉?3種類の衣づけで違いを徹底比較!
今回は汁のある料理にとろみ付けをしたいときの片栗粉の量にテーマをしぼって書きます。
料理にとろみ付けをしたいときの片栗粉の適量は?
料理に出てくるお水の量によっておおよその片栗粉の量は決まっていて、
天津飯のあんや、みたらし団子のたれのようなしっかりしたとろみを付けたい料理には
・水200mlに対して、片栗粉大さじ1+水大さじ2
これが、わりとしっかりめのとろみがつく、あんかけなどに適した濃度になります。
ゆるくとろみがついたスープや汁物のような料理には、わたしは
・水400mlに対して、片栗粉大さじ1+水大さじ2
をだいたいの目安としています。ごてごてしないとろみなのですが、とろみのおかげで汁物が冷めにくくなり、冬場には特にうれしいですよね。
ただ、中に入れている野菜や豆腐から出る水分や、どれほど煮込んで水分が蒸発しているかによって、入れる量は調整しなくてはいけません。
なので用意した水溶き片栗粉を少しずつ入れて、入れすぎないように、またとろみが足りなければ少し足す、ということを念頭に置いておいてください。
水溶き片栗粉の作り方と使い方
水溶き片栗粉ですが、
1. 片栗粉は小さな器に入れ、倍量の水であらかじめ溶いておく(片栗粉が大さじ1なら水は大さじ2)。片栗粉はすぐに沈殿してしまうので、入れる直前にもう一度かき混ぜ、流し入れる。
2. 鍋の中を絶えずかき混ぜながら水溶き片栗粉を流し入れる。片手でかき混ぜつつ、もう一方の手で水溶き片栗粉を持ち、一か所に集中的に入れないように全体に入れる。
3. 全部入れ終わった後、すぐに火を止めず、1~2分ほどしっかり加熱して片栗粉にも火を通すようにする。こうすることでしっかりとしたとろみがつく。
こんな感じで意識しながら調理してみてください。
「干ししいたけのあんかけうどん」レシピ
それでは、ポイントを踏まえながらさっそく実践してみましょう。冬におすすめのとろみのついたあんかけうどんのレシピです。
今回は、ゆるくとろみがついた状態にしたいので、「・水400mlに対して、片栗粉大さじ1+水大さじ2」という条件に当てはめると、材料の水が「水…800ml」となっているので「片栗粉大さじ2+水大さじ4」という計算になります。
分量
2人分
材料
- 豚薄切り肉…140g
- 干ししいたけ…大2枚
- だし昆布(5cm四方くらいのもの)…1枚
- 水…800ml
- 片栗粉…大さじ2(大さじ4の水で溶く)
- 青ねぎ…お好みの量
- A
酒…大さじ2 - しょうゆ…大さじ1
- 塩…小さじ1
作り方
1. 鍋に分量の水と昆布、干ししいたけを入れて常温に30分ほど置く(冷蔵庫で半日くらい置いてもいいです)。干ししいたけがやわらかくなったら取り出し、軸を切り落として4等分に切り、鍋に戻す。豚肉は食べやすい長さに切る。
2. 鍋を中火にかける。煮立ってきたら豚肉を入れ、あくをすくう。

中火から弱火で5分ほど煮たらAを入れ、水溶き片栗粉でとろみをつける。

追加で5分ほど煮る。冷凍うどんは煮ている間に電子レンジで3分ほど温め、器に入れておく。
※5分ほどすると水溶き片栗粉の粉っぽさがなくなり、つゆに透明感が出ます

3. うどんの入った器に2の出汁をたっぷりとかける。お好みで青ねぎの小口切りをのせる。

干ししいたけと昆布のダブルの旨味のうどんだしが、片栗粉でしっかりとろみがつくことで、ちょっと冬っぽいおうどんになります。
仕上げにしょうがのすりおろしをのせてもおいしいですよ!
途中からとろみがなくなってきたら…?
ちなみになんですが、片栗粉でとろみをつけた料理を食べていると、途中からとろみがなくなってサラサラになることがありますよね。
これは唾液の中に含まれるアミラーゼという酵素のせいで片栗粉の主成分であるデンプンが分解されてしまうからなのですが、とろみを保つ方法は上記にあるように片栗粉を入れた後にしっかり加熱すること(ただし、加熱し過ぎには注意。)。そして料理を70℃以上に保つことなどがあります。
70℃以上に保ちながら食べるのはなかなか難しいので、料理を入れる前にあらかじめ器を温めておいたり、お鍋から味見するときは直接ではなく取り皿を使うなど気をつけましょう。食べるときにもなるべく唾液が入らないように取り皿を使って食べると、よりとろみが持続されるかもしれませんね。